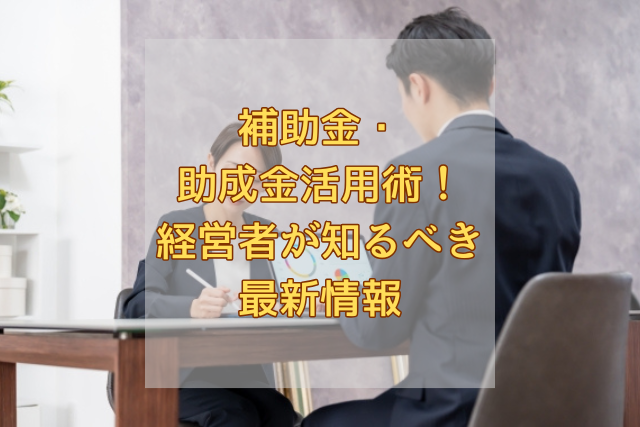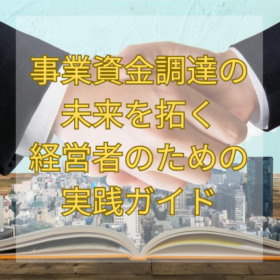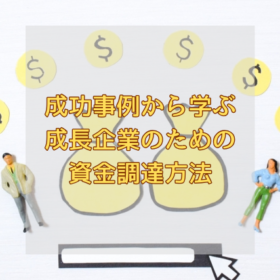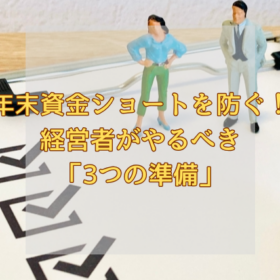民間企業を経営する上で必要になる資金は基本的に自力で調達する必要があり、経営者は常に資金需要とその確保のバランス調整に意識が向いています。
自力調達が基本であるのは当然として、日本には企業経営を資金的に支える仕組みが多くあり、補助金や助成金もの一つです。
経営者としては補助金や助成金を上手に活用して資金繰りの一助とすることが望まれます。
本章ではこれらの活用術や最新事情について解説していきます。
■補助金・助成金とは

補助金も助成金もどちらも国や自治体が提供する施策で、一定の枠組みに沿った事業を行う事業者に対して支給される金銭的な支援策の位置づけです。
補助金は主に経済産業省、助成金は主に厚生労働省が所管する事業ですが、実際には県や市区町村の単位で多様な補助金、助成金が存在します。
国の施策のみに絞って言えば、補助金は経済産業省が所管する事業で助成金は厚生労働省が所管しています。
所管官庁が違うので目的や性質が異なり、経産省所管の補助金はザックリ言うと攻めの経営拡大を目指す事業者が対象になります。
厚労省所管の助成金は労働者が働きやすい環境を整えたり、賃金UPを積極的に行う事業者に対してその費用の一部を助成するものです。
補助金も助成金もどちらも返済不要であるため、対象になるようであればぜひ活用するべきです。
■資金繰り改善だけでない意外なメリット

補助金や助成金は金銭的なメリット以外の間接的な効果も期待できます。
補助金や助成金は政府や自治体、公的機関から支給されるため、選定された企業はそのプロセスを通して信頼性が証明されることになります。
その結果、金融機関や取引先からの信用が厚くなり、融資条件の改善や取引拡大の可能性が広がります。
実際、補助金や助成金を獲得した実績がある企業は公式WEBサイト上で、あるいは様々なシーンで折に触れてその事実を公表するようにしていることが多いです。
補助金については経済上の間接効果として取引先にも恩恵をもたらします。
受給した資金を活用して設備投資を行う企業があれば、機器の提供やサービスを請け負う取引先にも需要が生まれます。
また補助金を受けた企業が業績を向上させることで、取引先にも安定した注文や新たなビジネスチャンスを提供する可能性があります。
このように補助金は一企業だけでなく経済活動全体の活性化にも寄与します。
■最近の補助金・助成金の性質動向

最近の補助金や助成金の動向については、成長分野への支援だけでなく、社会的な課題を解決するための多様な分野への支援が増えている印象です。
自治体が所管する補助金、助成金事業では高齢者向けサービスや子育て関連サービス、防災訓練など、地域の安心安全を支える分野への支援が充実してきている印象です。
こうした事業を主軸とする事業者は地元密着で活動する企業が多く、比較的小規模のところが多いと思われます。
資金体力的には余裕のないことが多いので、地元自治体の支援策は積極的に検索し利用の可否を検討することをお勧めします。
自治体提供の補助金や助成金は担当部署が分かれていて直接の窓口相談は効率が悪いことがあります。
支援策をまとめて検索できるサイトを載せておきますので参考にしてください。
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi/articles?category%5b%5d=2
ただし現存する全ての施策が必ず反映されているとは限りません。
地元の商工会や行政書士、税理士などが施策をまとめて相談に応じてくれることもあるので、検索の初手として専門家や専門機関を探してみても良いでしょう。
国が所管する事業は自治体のプランよりは格式ばったものが多い印象ですが、昨今は国際化と雇用拡大の促進を目的にして海外展開を目指す中小企業への支援策が増えている印象です。
■補助金・助成金で知っておくべきポイント
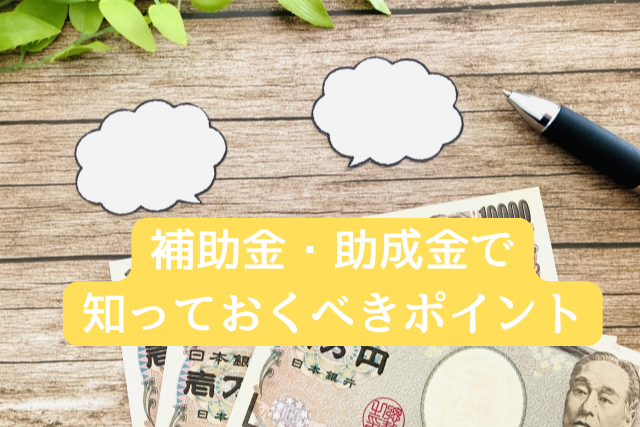
ここでは補助金や助成金を活用する際に知っておくべきポイントについて見ていきます。
①後払いの仕組みであること
補助金や助成金は一般的に費用の支出後に申請し、その後に給付される「後払い」の仕組みが基本です。
そのため補助金や助成金の受給を見越して事業を進める際には、自己資金や他の資金調達手段を事前に用意する必要があります。
銀行融資のように事業資金として事前に受け取れる性格のものではないということは理解しておかなければなりません。
②事業内容の適合性
補助金や助成金はそれぞれの制度ごとに目的や対象となる事業内容が明確に定められています。
ですから利用申請前に自社の事業内容が支援施策に合致しているかどうかをしっかり確認することが重要です。
制度に適合しないと申請が却下される可能性があるため、準備に掛けた手間や時間、費用が無駄になってしまいます。
③給付後の制限
受け取った資金には一定の用途制限が設けられることが多く、給付後も使用報告や監査の対象となる場合があります。
また助成金を利用した設備やサービスは一定期間売却や用途変更が制限される場合もあり、これに違反すると給付金の返還義務が生じることがあります。
④資金調達手段としての限界
補助金や助成金は魅力的な資金調達手段である一方で、必ずしも確実性があるものではありません。
申請が競争型であったり、予算枠が限られていたりする場合が多いからです。
助成金は給付が小口であることが多く、まとまった資金源にはならないことも多いです。
そのためこうした公的支援だけに頼らず、他の資金調達手段と組み合わせて資金管理のリスクを分散するのが賢明です。
■まとめ
本章では補助金や助成金の活用術、最新事情について見てきました。
補助金や助成金は国や自治体が提供する企業への支援施策で、返済不要の資金を受け取れる有難い仕組みです。
大きく国の施策と自治体の施策で分かれ、国の方は経産省や厚労省が所管し、それぞれの目的に沿った施策を提供しています。
自治体の方はより地域未着型で、市民に身近な事業内容を手掛ける事業者向けのプランが多くなっています。
いずれにしても、金銭的メリットだけでなく信用増強など間接的なメリットもあるので利用できるならば利用すべきです。
行政窓口や商工会、地元の専門家などに相談して利用できそうなものがないか検討してみましょう。